高度な医療を提供する大学附属病院および大規模病院にとって、ウェブサイトは単なる情報インフラを超え、病院の理念、技術力、そして患者さんへの深い配慮を伝える最前線のブランド資産と言えます。
日々進化する先進医療の提供、地域医療連携の中核としての役割、そして未来の医療者を育成する教育・研究機関という多岐にわたるミッションを抱える大学病院のウェブサイトには、一般のクリニックサイトとは異なる、複雑かつ高度な設計思想が求められます。
このデジタル時代において、優れた大学病院サイトは、まず第一に患者さんのことを考え「不安」を「安心」に変える役割を担わなくてはなりません。サイトデザイン、クリエイティブ、そしてコンセプトは、来院前から病院への信頼感を築き上げ、最終的には病院のブランド価値と経営戦略に直結するような重要な要素です。
本記事では、この重要な役割を果たすために、日本の主要な大学附属病院のウェブサイトがどのような「直感的なデザイン」「高いユーザビリティ」「明確なブランディング」を実践しているのかに着目し、その共通項から次世代のウェブサイト戦略の鍵を探っていきたいと思います。
患者さん中心の導線・ユーザビリティ・ブランディングを実践する大学病院のウェブサイト5選
順天堂大学医学部附属順天堂医院
https://hosp.juntendo.ac.jp/

導線・UX(直感性)
利用者属性(初診/再診/面会)に基づく巨大な入口をトップページに設け、ユーザーの情報探索の迷いを最小化する優れた情報アーキテクチャを実践しています。
スマホ・ユーザビリティ
レスポンシブデザインが洗練されており、スマホ利用者が増える現代において、利便性を最優先した設計です。文字サイズやコントラストも十分に確保されています。
ブランディング(教育・専門性)
「研究・研修」といったカテゴリが明瞭であり、大学病院としての教育的側面を明確なコンテンツで提示しています。

グローバルナビゲーションに患者さんを中心に使いやすい病院メニューがあり、ここでダイレクトに、欲しい情報にたどり着けることができる仕様。また、AIコンシェルジュによる初診受付を導入していることで、医療現場全体の効率化と質の向上を目指しているようです。
日本大学病院

導線・UX(直感性)
装飾を排したクリーンで機能的なデザイン。主要な情報ブロックをファーストビュー内に配置することで、緊急性の高い情報へのアクセスを容易にしています。
スマホ・ユーザビリティ
シンプルなレイアウトのため、スマホでも読み込みにストレスなく、高い可読性も実現。メニュー内も患者さんファーストの情報設計で急病時にもストレスなく情報に到達できそうです。
ブランディング(教育・専門性)
「地域医療連携」と「臨床研究」への導線を明確化し、大学病院の持つアカデミックな背景と地域への貢献度を両立させています。

グローバルナビゲーションのメニューは、患者さんファーストの情報設計で迷わず使いやすい仕様になっていて、この他に医療情報を検索できるコーナーがあり、「病気・疾患情報」「診療科・部門」「担当医情報」が検索でき、様々な角度で医療情報へのアプローチが可能です。
東京女子医科大学病院

導線・UX(直感性)
情報の優先順位付けが徹底されており、シンプルで使いやすい構造。利用者が知りたい情報に集中できるよう配慮されています。
スマホ・ユーザビリティ
落ち着いたトーンと適切な行間・文字サイズが、特に女性や高齢の患者さんに配慮した高いユーザビリティを示しています。
ブランディング(教育・専門性)
女性医療を核とした専門センターの紹介が充実しており、病院のユニークなアイデンティティと専門分野での強みを効果的に発信しています。

グローバルナビゲーションに患者さんを中心に使いやすい病院メニューがあり、ここでダイレクトに、欲しい情報にたどり着けることができる仕様。また、AIコンシェルジュによる初診受付を導入していることで、医療現場全体の効率化と質の向上を目指しているようです。
横浜市立大学附属病院
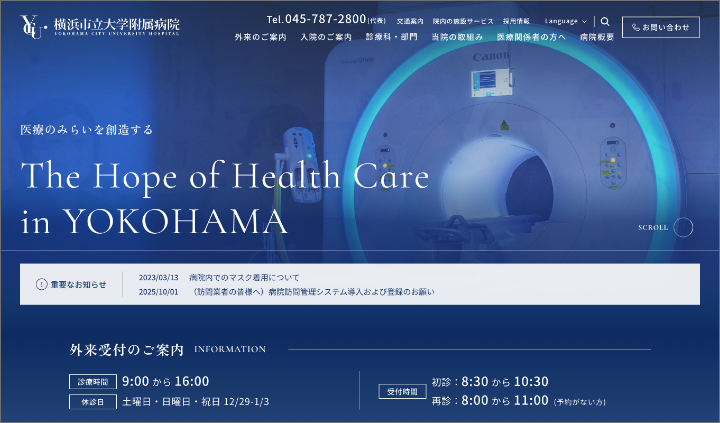
導線・UX(直感性)
マリンブルーを基調とした横浜らしい配色が、海沿いの立地を連想させる爽やかさが特徴的です。シンプルにセグメント分けされているので、主要な受診機能への導線も分かりやすいです。
スマホ・ユーザビリティ
コントラストが高く視認性に優れ、スマホでもスムーズな予約や情報検索を可能にするユーザーフレンドリーな設計が見られます。
ブランディング(教育・専門性)
先進医療や専門性の高いセンターの紹介に注力し、地域の中核病院としての高度な専門技術を訴求しています。

PCサイトでは、ヘッダーに連絡先(TEL)が大きく表示され、診察に関する情報は、スクロール内でおさまるようなデザインされ、スマホサイトでも右上のメニューを開けば、すぐに連絡(TEL)できる仕様になっていて、患者さんの行動に配慮したUX設計になっています。
千葉大学医学部附属病院

導線・UX(直感性)
患者、医療関係者、学生といったマルチなターゲットを想定した導線設計。特定機能病院として、それぞれのニーズに応える高い情報整理能力を発揮しています。
スマホ・ユーザビリティ
情報量の多さを適切に捌く整理されたデザインで、スマホでも必要な情報が探しやすい構造的な優位性を持っています。
ブランディング(教育・専門性)
「高度医療」に関する情報を充実させ、最先端の研究と臨床を担う大学病院としてのブランド力を強く打ち出しています。

地域の先端医療を担う病院にありがちな先進的なイメージのウェブサイトではなく、患者さんや地域に寄り添うあたたかみのあるイメージで、トップページは診療案内と予約サービスのボタンが目立つように固定表示され、患者さんに迷わせないよう直感的に操作できるようになっています。
まとめ
今回考察した大学病院のウェブサイトが共通して実践しているのは、「患者さんを最優先した情報設計」です。これは、単に見た目の美しさを追求するデザインではなく、情報に迷わせない設計思想に裏打ちされています。
大学附属病院のような複雑で膨大な情報を扱う医療機関において、患者さんにとって必要な情報をストレスなく提供し、直感的な操作で目的を達成できることは、来院への障壁を取り除くための最重要戦略です。
これは、すなわちUX(ユーザーエクスペリエンス)デザインを核に据えることで、
「先進医療への期待を高める」「教育・研究機関としての信頼性と透明性を担保する」そして、「来院前の不安を最小限に抑える」という多角的な課題を解決することに繋がります。
大学附属病院は、ウェブサイトデザインにおいても、この必要な情報の提供と直感的な操作こそが、患者さんの信頼と安心を築くUXデザインの肝であることを認識し、今後のデジタル戦略を推進していくべきでしょう。
